遺言書作成
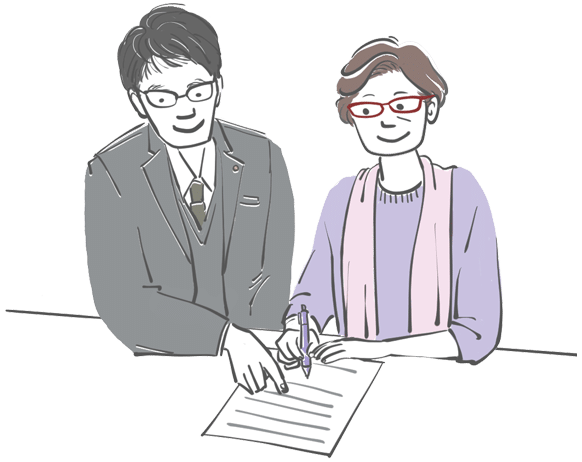
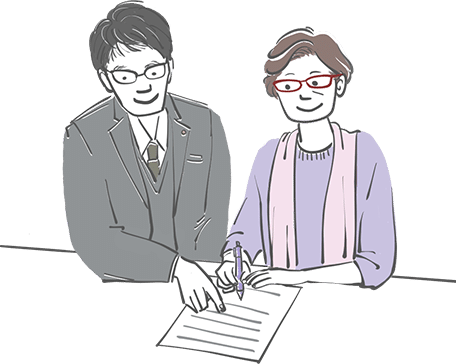
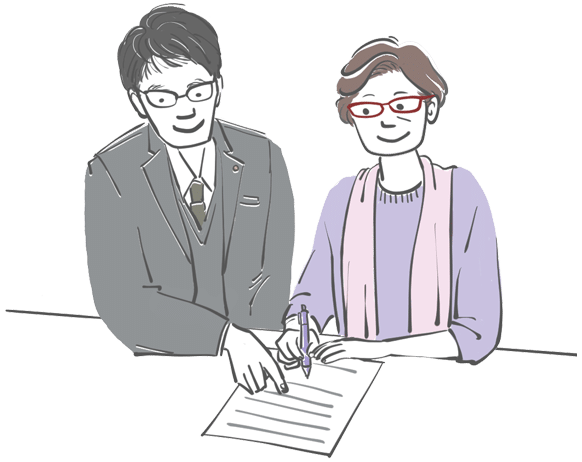
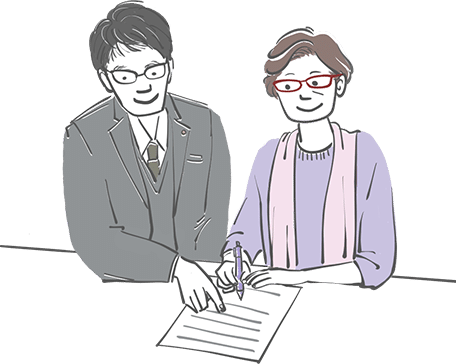
「終活」という言葉もだいぶ定着してきましたが、自身の遺言を用意している人はまだあまり多くありません。
遺言はその言葉の雰囲気が「遺書」に近いこともあり、あまりいい印象は持たれないかもしれません。しかし遺言にはとても大切な意味があります。
仲のよかった家族が、相続財産の分配を巡って争い、修復不可能なほど関係がこじれてしまった…。そうした例は多くあります。
遺言を用意しておけば、遺産分割の手続が大幅に軽減され、遺族の負担を減らすことができます。また、それによって遺族間の争いを未然に防ぐことにもつながります。
遺言には、今まで家族に伝えられなかった気持ちを「付記事項」として記載しておくことができます。
面と向かっては伝えにくい感謝の気持ちや、家族を大切に思う心を、今のうちに形にしておきましょう。
遺言書を法律上有効なものとするためには、民法の定める書式等に従う必要があります。そうした形式が守られていないものは遺言としての法的な効力を持たないので、せっかくご自身で用意した遺言書も、法律上は何の効果もない、ということもあり得ます。また、遺言書の中で不動産を正確に記載しておかないと、実際の名義書換登記の際に遺言書を用いることができず、遺族に過分の負担を強いることとなってしまいます。
有効な遺言書を作成するためにも、遺言作成や不動産登記に詳しい司法書士のアドバイスを受けましょう。
遺言書は大きく分けると、以下の2種類になります(秘密証書遺言はここでは扱いません)。
当事務所では、より安心な公正証書遺言の作成を強くおすすめいたします。
ここでは公正証書遺言の作成手順をご紹介いたします。
遺言書の内容を決めるため、現在の財産を洗い出します。その上で、誰にどの財産を相続させるかを決定します。
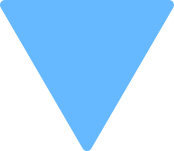
相続人を特定するための戸籍謄本や、不動産の固定資産税評価証明書等が必要となります。
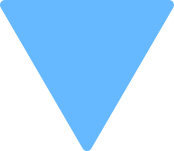
遺言書の内容を決めるため、現在の財産を洗い出します。その上で、誰にどの財産を相続させるかを決定します。
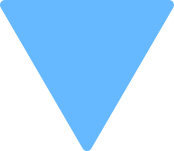
公正証書遺言を作成するには証人2名が必要となります。相続人となる可能性がある者や未成年などは、証人になることができないため注意が必要です。
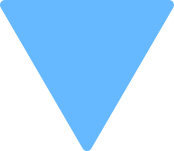
公証役場へ出向くのが難しい場合は、公証人がご自宅まで出張することもあります。その場合には別途出張日当がかかります。
当事務所にご依頼頂ければ、スムーズに公正証書遺言が作成できるよう、上記の手続を支援いたします。
以下は公正証書遺言作成をご依頼頂いた場合の費用です。自筆証書遺言作成支援については別途お問い合わせください。
※基本手数料については、相続関係の複雑さや不動産の個数などによって異なる場合があります。
※公証人手数料は、例えば財産額が100万円以下の場合は5,000円+遺言加算11,000円の金16,000円となります。